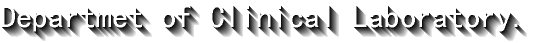

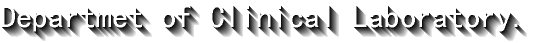  |
| |HomePage |About us |Units |Information |Documents |Events |Links |Limitted |Person |Work | |
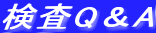
A. サイトメガロウイルス(Cytomegalovirus,CMV)は,分類上ヘルペスウイルス科(herpesviridae)に属するDNAウイルスである。日本人においては,成人になるまでに90〜95%の人が感染しており,ほとんどの人は不顕性感染の型をとり,ウイルス抗体陽性となっている。
CMV感染症の診断は,ウイルス学的所見と臨床所見の両者に基づく。とくに複数の部位からCMVが分離される(多臓器感染),末梢血中にCMV陽性の多形核白血球が検出される(抗原血症,antigenemia),血漿中にCMVのDNAが検出される(DNA血症)などのウイルス学的所見は活動的なCMV感染の指標となる1)。 ウイルス抗原検査法には,シェルバイアル(shell vial culture)法やCMV anti-genemia法などがある。
CMV antigenemia法は,CMVが白血球(ほとんどが好中球)に感染したとき,きわめて早期に発現するCMV抗原をモノクローナル抗体で染色し,検鏡する方法である。検体としては,末梢血を用いる。通常50,000個の細胞をカウントし,陽性細胞の数で結果を示す半定量的方法である。この方法は,現在のところ,検出感度,特異性ともに高い検査法とされている。直接にCMV感染症を診断する方法ではないが,臨床症状や経過とよく相関することや,CMV感染症の症状が出現する以前に陽性になることから,臨床的に早期診断ができる検査法として重要な位置を占めつつある2)。
CMV抗原としては,early antigenやCMVビリオン(virion)を構成するテグメント(tegument)のlower matrix protein(LM,phosphoprotein,pp65;63kD)のpp65 抗原がある。
Pp65 抗原に対するモノクローナル抗体にはC10/C11(Theら,Biotest,Clonab),C12,1C3(Biosoft),HRP-C7(南嶋ら)などがあるが,このうちサイトメガロウイルス抗原検査法としてC10/C11とHRP-C7を外注業者が取り扱っている。
A. JC ウイルス(JC virus, JCV)は,パポバウイルス科(papovaviridae)のポリオーマウイルス属(polyomavirus)に属する環状2本鎖のDNAウイルスである。
ポリオーマウイルスには,このほかにsimian virus 40(SV40)とBK virus(BKV)がある。
進行性多巣性白質脳症(progressive multifocal leukoencephalopathy, PML)1)-4)は,本来病原性の低いJCVが免疫低下などを誘因として病原性を発揮する日和見感染症で,JCVが中枢神経のoligodendrogliaに感染し,大脳皮質下白質に多巣性の脱髄病巣を生じ,進行性の精神障害,運動麻痺,運動失調,視覚異常などを呈するスローウイルス感染症と考えられている。
従来はきわめて稀な疾患で,100万人に1人位の発症率といわれていたが,HIV感染の流行に伴って増加している。とくにAIDS患者での PMLの発生率は3.8%と非常に高いことが注目されている5)。
JCVは,14歳までの小児の65%が抗体陽性,50歳代の成人では75%が陽性になっているといわれる。したがって,JCV抗体測定の臨床的価値は低い。また,JCVは健常人の尿中にもしばしば検出されている。しかし,健常人に比べて,PML患者から分離されたJCVのDNAは,調節領域に多様性をもっていることが認められており,これがPML発症に関わっていることが推測されている。
確定診断は,従来脳生検により病巣を病理学的に診断することであったが,近年,髄液を用いたPCR法でJCV-DNAを検出する方法が普及した。しかし,一般的なPCR法では,多くの健常人に不顕性感染している場合,偽陽性が問題になる。これに対しては,JCV-DNAの調節領域を含む部位を増幅し,PML型JCVを確認する方法が報告されている4)。
JCVの脱髄形成機構については,JCVのT抗原がミエリン鞘の構成成分であるミエリン塩基性蛋白(MBP)遺伝子に直接あるいは間接に影響を及ぼし,ミエリン形成不全が起こり,その結果神経症状が出現することが推測されている。
 : 411-417,1999.
: 411-417,1999.
 : 427-430,1999.
: 427-430,1999.
A. エコー ウイルス(echovirus, EV)は,ピコルナウイルス科(picornaviridae)のエンテロウイルス属(enterovirus)に属する1本鎖のRNAウイルスである。
ウイルスが分離された初期の頃にはヒトの疾患との関係が明らかでなかったので,Enteric Cytopathogenic Human Orphan viruesの頭文字をとってエコー(ECHO)と名付けられた。その定義は,ネズミの乳児やサルで病原性をもたないことであった。元々,エンテロウイルス属はポリオウイルス(poliovirus),コクサッキーウイルス(coxsackievirus),エコーウイルスに分類されていたが,エコーウイルスに病原性があるものが見つかり,また,逆にコクサッキーウイルスでネズミに病原性をもたないものが発見されて混乱をきたしたため,1970年以後に発見されたエンテロウイルス属は単にエンテロウイルスに68番から番号をつけることになった1)。
エコーウイルスには,1?9,11?27,29?33の31型がある(10型はレオウイルス,28型はライノウイルス1型,34型はコクサッキーA群ウイルス24型と同じ)。コクサッキーウイルスA群は,1〜22型,24型(23型はエコーウイルス9型と同じ),コクサッキーウイルスB群は1〜6型,エンテロウイルスは,68〜71型(72型はA型肝炎ウイルス),ポリオウイルスは,1〜3型がある。
エコーウイルスによる感染症は,中枢神経感染症か皮膚疾患まで多彩な臨床症状を示すが,同様な疾患を惹起するのもにコクサッキーウイルスがあり診断に困難なことも多い2)。
無菌性髄膜炎(aseptic meningitis)は,ウイルス性髄膜炎(viral meningitis)と同義的に用いられる。髄膜炎の原因は大部分が感染性であり,圧倒的にウイルス性が多い。ついで細菌性,結核性,真菌性の順となる。
無菌性髄膜炎の主な症状は,発熱,頭痛,吐き気,嘔吐などである。項部硬直などの髄膜刺激症状を伴うが,これが認められない場合もある。髄液検査所見は,圧の軽度上昇,リンパ球優位の中等度の細胞増加(5?500個/mm3),糖は正常,蛋白は正常もしくは軽度上昇を示すことが多い。
エコーウイルスでは,(12),24,26,29,32,(33)以外のすべてでヒトの髄膜炎,脳炎を起こすことが知られている。3,18,19型では,大流行の原因になったことがある3)。起因ウイルスとして最も多く認められるのはコクサッキーウイルスB5,エコーウイルス4,6,9,30である4)。 わが国での状況については,国立感染症研究所・感染情報センターのホームページ(週別無菌性髄膜炎患者からの主なウイルス分離報告数,2000〜2002年 (2002年10月24日現在,http://idsc.nih.go.jp/prompt/graph/et8j.gif) ,無菌性髄膜炎患者から分離されたウイルス,1997〜2002年 (2002年10月24日現在, prompt/graph/et9j.gif)を参照されたい。
 :448-4452,1999.
:448-4452,1999.
A. ヒトがウイルスの感染をうけると,一定時間後に血清中にそのウイルスと結合し,ウイルスの細胞への感染を阻止する抗体,すなわちウイルス中和抗体が出現する。この反応がウイルス中和反応(Neutralization test:NT法)で,ウイルス抗体検査法の中で最も型特異性が高い方法である(ヘルペスの 型と
型と 型は例外)。IgG,IgM,IgAの抗体のそれぞれが中和活性をもっている。
型は例外)。IgG,IgM,IgAの抗体のそれぞれが中和活性をもっている。
NT法では,段階希釈した被検血清とウイルスを混合し,抗原抗体反応を行わせたのち,培養細胞に接種し,培養を行う。一定期間後観察を行い,細胞変成効果(cytopathic effect:CPE)の有無をしらべる。CPEがなければウイルスの増殖が抑制されたことになり,中和抗体陽性と判定される。
感染価(ウイルス力価)は,50%終末点(50%tissue culture infectious dose, TCID50)をReed-Muench法によって求め,その希釈倍率をもって抗体価としている。 単純ヘルペスの場合,攻撃ウイルスの力価は1,000TCID50が用いられている。
中和反応において,中和反応混合物に補体を添加すると中和抗体価が上昇することが多くのウイルスで知られ,とくにヘルペスウイルスの感染初期の診断に応用されている。ヘルペスウイルスの場合,補体を加えないで測定される中和抗体価(Neutralizing antibody:N)と補体を加えて得られる中和抗体価(Complement requiring neutralizing antibody:CRN)の間には次のような関係がある。
CRN:Nの比が4またはそれ以下の場合 IgG
CRN:Nの比が8またはそれ以上の場合 IgM(または初期感染のIgG)
HSV- |
HSV- |
|||
|---|---|---|---|---|
| N | CRN | N | CRN | |
HSV- 既往の潜伏感染者 既往の潜伏感染者 |
64 | 256 | 8 | 32 |
HSV- 初期感染直後 初期感染直後 |
4 | 64 | <4 | 8 |
| 初感染後、潜伏感染者にならずに長年月日経過して低抗体になったもの | 8 | 16 | 4 | 8 |
| 無抗体者 | <4 | <4 | <4 | <4 |
A. 1956年,AdamsとPurvesがGraves病(Basedow病)患者の血中に,TSHとは異なる甲状腺機能亢進を起こす因子を見つけ,long-acting thyroid stimulator(LATS)と命名した。ついで,1964年,LATSはimmunoglobulin(IgG)であることが発見され,のちにthyroid stimulating immunoglobulinあるいはTSAbとして知られるようになった。Graves病は,TSH受容体に対する自己抗体(thyrotropin-receptor antibodies,TRAb)の甲状腺刺激作用に関連することが明らかになり,TSH受容体を介する自己免疫疾患と考えられるようになっている。
LATSはあくまでもマウスを用いたbioassayによるものであり,煩雑で,Graves病に低感度(未治療で20%程度の検出率)で,精度も低いなど問題が多く,ほとんど測定されなくなった。しかし,これを契機にTSH受容体抗体(TRAb)に関する基礎的・臨床的研究が進んだ。
TSHは,細胞膜上にあるTSH受容体の細胞外ドメインに結合し,G蛋白を介してadenylate cyclaseを活性化し,TSHの細胞内伝達物質として働くcyclic AMP( cAMP)の産生を増加させる。
TRAbの測定は,標識TSHとTSH受容体の結合への影響をみるものと,cAMP産生を指標とするものに大別される。 現在行われているTRAb測定法には,つぎの3つがある。
 TSH-binding inhibition assay(TSH結合阻害抗体,thyrotropin-binding inhibitory immunoglobulin, TBII)
TSH-binding inhibition assay(TSH結合阻害抗体,thyrotropin-binding inhibitory immunoglobulin, TBII)
 Thyroid-stimulating antibody assay(甲状腺刺激抗体,TSAb)
Thyroid-stimulating antibody assay(甲状腺刺激抗体,TSAb)
 TSH-blocking antibody assay(甲状腺刺激抑制抗体thyroid stimulation blocking antibody, TSBAb, TBAb)
TSH-blocking antibody assay(甲状腺刺激抑制抗体thyroid stimulation blocking antibody, TSBAb, TBAb)