第18回香川県小児保健協会研究会開催に際して
目と目を合わせて1日100回「好き」と言いましょう。それがビタミン愛(EYE)!!
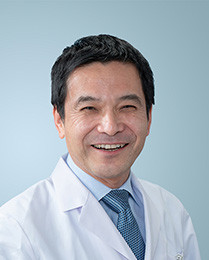
一か月健診をしていますと、目を全く凝視できない赤ちゃんがいます。視覚障害がある様子ではなく、待合での母親の様子を観察していますと殆どスマートフォンを見ているばかりで、赤ちゃんに話しかけたり、あやしたりする様子は認めませんでした。反対にしっかり追視が可能な赤ちゃんがおり、お母さんがしっかり目を合わせて話しかけている様子が伺えます。またお母さんにきょうだいの有無をお聞ききしますと、殆どの赤ちゃんにきょうだいがおり、いつもこどもたちが赤ちゃんと目を合わせて遊んでいるそうです。赤ちゃんは生まれてきて様々な視覚刺激を受けて、嗅覚や味覚が優位な脳機能から視覚優位の脳機能へと変化します。その過程では様々な神経機能を司る細胞の増加や髄鞘化、シナプスの増加そして減少といったダイナミックな大脳を含む神経系の成長と発達(発育)が促され、特に大脳の成長速度は生後6月頃が最大となります。その発育には自らの発育と共に、周囲からの刺激がとても重要です。つまり人間は出生後から人間と目と目を合わせて呼応して、神経系の発達を促さなければならないのです。その神経系での発達には計算や言語を制御する部分と心の部分があり、特に生後では心の発達に関係する脳の中心部の発達が優位なため、この時期に赤ちゃんの目を見ながらの心の教育が重要だと考えられます。
今回の小児保健研究会のテーマは「みんなでビタミン愛(EYE)まつり」としました。新生児期には母乳栄養を中心とした栄養と、ビタミンK、ビタミンDの補充が重要であると言われていますが、何よりもまず赤ちゃんと目と目を合わせて、「大好き」と、一日に何回も言うことが重要だと考えるからです。これにより母親や父親の母性や父性が育ち、虐待防止に繋がる可能性もあり、双方向性の効果があります。これが「ビタミン愛(EYE)」です。またビタミンは生体が自ら作れるものではないため、常に周囲から与えられ続けなければならないのです。このため赤ちゃんへビタミン愛を与えると同時に、母親や父親へのサポートも重要です。
心の教育は脳科学ではその客観的指標がないために評価が難しいですが、人間が誕生した時から赤ちゃんはヒトの目を見るように遺伝子にその機能が情報として存在し、世代を超えてその教育がなされてきました。今回の研究会では子育ての原点として、目と目を見つめて声かけをする重要性を改めて理解し、こどもの心の教育について考えたいと思います。
香川県小児保健協会会長
日下 隆

